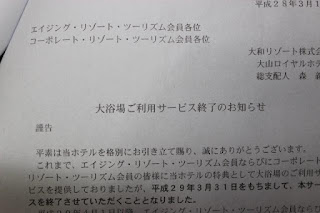烏賊焼きそば屋さんは約束通り、ガーデンプレイスにきて私と雅子のために紅ズワイ蟹を持ってきてくれた。
鰺の新鮮な魚をお土産にいただく。
早速刺身にしていただきました。
この隣人との約束の行為にわたしは感動を覚える。
人と人が暮らしてゆくのに感動を覚えるこの約束は、いったいなにに依拠しているのか知りたくなった。
ハンナ・アーレントは人間の行為について考察し赦しと約束の人間のtalentタレント能力を、人間の行為(複数の人びとの共生)に潜む難題を救済するものとして(為されたことの取り返しのつかなさと赦しの力、行いの予測のつかなさと、約束の力)、として興味深い言葉を著わしている。
赦しは、政治的なものにおいて、まじめに考えられたことが一度もなかった。赦しが宗教上の文脈で発見され、「愛」に左右されると見なされたという理由だけで、そうであった。
これと違って、約束を交わし、守るという能力、および、未来のことを確固たらしめるという、約束に内在する力は、伝統からうかがえる限りでの政治の理論と実践において、並外れた役割を果たしてきた。
この伝統の起源に関して言えば、ローマ法が拠りどころとする契約と協定の神聖不可侵性- pacta sunt servanda つまり、契約は守られるべし - を思い浮かべることができるし、同様に、ウルの人アブラハムを引き合いに出すこともできよう。
彼アブラハムは、「故郷を捨て、親族と別れ、父の家を出て」見知らぬ国々へ赴いては、その行くところどこでも、協定を結ぶことで紛争を調停した。アブラハムが異国に移り住んだのは、あたかも、たがいに約束する力を試すこと、また、約束によって人間世界のカオスのうちへ導き入れられる秩序を試すこと、ひとえにこの一事のためであったかのようである。そしてついには、彼の試みが「確証」されるのを目の当たりにした神自身と同盟を結ぶに至ったのである。
ともあれ、古代ローマ以来、契約理論は、政治思想の中心に位置してきた。この伝統が意味するのは、約束する能力は中心的な政治能力であると見なされてきたということ、このこと以外なにものでもない。
未来のことは予測がつかず、霧のように不確かで分りづらい。五里霧中のこの状態をあちこち晴らし四散させるのが、約束の働きである。では、そのような予測のつかなさが昂じるのはなぜか。その理由は、一つには、人間の心は底知れず不可解だからであり、「強情でありかつ弱気なもの」だからである。
予測のつかなさの根源は、人間という存在が原理的に変わりやすく当てにならないという点にある。自分が明日誰になっているか、今日請け合うことすらできないのが人間なのだ。
他方で、未来の予測のつかなさは、複数性という媒質によるところ大である。行為は複数性のうちを動くと言えるのは、何らかの行いの帰結が、じつのところ、その行い自身から生じるのではなく、その行いが組み込まれる当の関係の網の目から、ないしは、等しい行為能力を持ち合わせている対等な者たちがたまたま一組の共同体を揃ってなすにいたった当のめぐり合わせの布置から、生じるからである。
人間は、自分自身を当てにすることができない。もしくは、同じことになるが、自分自身を完全に信用することができない。だがこれは、人間が自由であることと引き換えに支払わなければならない代償なのである。
また人間は、自分自身の為すことを意のままに支配する主人であり続けることができず、帰結を知るよしもなければ、将来を当てにすることもできない。だがこれは、人間が他の同等の人びととともに世界に住んでいることと引き換えに支払わなければならない代償なのである。
言いかえれば、その代償を払ってこそわれわれは、たった一人でいるのではないのだという喜びを、そして人生はたんなる夢なのではなくそれ以上の何かなのだという確信を享受しうるのである。
約束を交わし、守るという能力が、人間事象の領域の枠内で果たすべき任務は、以上の二重の不確実性を克服することである。
ただしそこには程度問題というものがある。つまり、約束の他にもう一つだけ別の方途があり、それは人間事象のうちに身分秩序といったようなものを持ち込むという自己支配および他者支配のことだが、この方途をとるには及ばない程度に抑える、ということが望まれる。
というのも、約束、ならびに約束から生じる協定や契約は、非-主権という条件のもとで与えられる自由に適合している、唯一の結束のかたちだからである。
主権が可能となるのは、多数のひとびとが、助け合ったり反目しあったりしつつもお互いどうし保証し合い、自分たちには予見できない未来の事情に向かってそれでもなお結束し合う場合だけである。
道徳Moralとは、ラテン語morsの複数形moresに由来する。「モーレス」とは、そのつど妥当する風習や慣習のことであり、それとともに、そこに含まれそのつどの態度ふるまいを定めるあれこれの尺度のことであり、そうであるからには当然、歴史的に持続しつつ変遷し、国ごとにズレがある。だが、われわれが道徳モラールという言葉で意味しているのは、そういう「モーレス」の全総計より以上であってよい。もしそうだとすれば、道徳は、すくなとも政治的領域においては、約束する力能にもっぱら拠らざるをえない。また、行為する存在であるかぎり人間がどうしょうもなく晒されるリスクや危険に遭遇する覚悟を決め、許し許され、約束を交わし守る、といった善意性に、もっぱら支えられざるを得ない。
ともあれ、許しと約束は、道徳の指針と言ってよい唯一のものである。だがその場合、道徳の指針とは、行為よりも高次の能力と称されているものとか、より高次の事柄と称されるものにふれる経験とか、そういったものから導き出され、行為の外側で獲得される尺度や規範なるものを行為にあてがうものではない。
道徳の指針はむしろ、行為と言論にそもそも乗り出したかぎりでの人びとの相互共存から、直接に生じてくるのであり、それはまるで、それ自体終わりのない新たなプロセスを始め、解き放つという能力のうちに組み込まれた制御器官であるかのようである。
この世には「奇跡」を成し遂げるという徹底してこの世的な能力が存在するということ、そして奇跡をもたらすこの能力こそ行為にほかならないということ、このことをナザレのイエスは知っていただけでなく、赦す力を、奇跡を成し遂げる者の能力と比較することで、それを言い表わしもした。
その場合イエスは、赦しと奇跡とを同等に扱い、この世的な存在である限りでの人間に帰せられる可能性と解したのだつた。
「生れ出ずる者」。「イエスは答えて言われた、『よくよくあなたに言っておく。だれでも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない』。」(ヨハネ3章3節)
生れ出ずる者の二重の意味=人が地上に誕生することと、復活すなわち人が聖霊により新しく始める行為。
生れ出ずる存在とは、行為といったようなものがそもそも存在しうるための存在論的前提なのである。
(それゆえ、イエスの物語が宗教上重要なのは、もちろん死者の復活に関わるが、政治哲学にとって格別の意義は、イエスの誕生と誕生性Geburtlichkeitに重点を置いていることにある。だからたとえば、ヨハン・ベーター・ヘーベルは「天からみおろし、われわれの道を眺めている」復活者キリストのことを、「生まれ出ずる者」となおも呼ぶことができたのである。それというのも、キリストは一個の「生れ出ずる者」としてのみ「生きている」からだ、と。)そもそも人間が生れてくること。またそれとともに、生れ出ずる存在のおかげで人間が行為しつつ現実化することができる新たな始まりも生まれること、ここに「奇跡」は存する。
行為のこの面が完全に経験されている場合のみ、「信仰と希望」といったようなものがはじめて存在しうるのである。
それゆえ、人間の存在のこの二つの本質的徴表について、ギリシャ人はほとんど何も知らなかった。ギリシャ人にあっては、忠誠と信仰は非常にまれで、政治的事象の進行にとっては無意味なものだったし、希望とは、人間の目を眩ませるパンドラの箱に由来する禍だったからである。
われわれはこの世で信頼を抱いてよいのだということ、そしてこの世に希望をもってよいのだということを、クリスマスのオラトリオが「よき知らせ」を宣べ伝えている次の言葉ほど、簡潔に美しく表現したものは、おそらくどこにもない。-「われわれに一人の子どもが生まれた」。
Chapelle de Potensac Medoc 2012 Delon
負い目ある人びとをわれらが許すごとくに、われわれの負い目を赦してくれる共同世界が、かりに存在しなかったとしたら、われわれは、われわれ自身のいかなる犯行も罪過も赦すことができないだろう。
なぜなら、自分自身の内部に閉じ込められてしまえば、犯された不正行為より以上の存在である人格が、われわれに欠けてしまうからである。
聖書より
「ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる。ひとりの男の子が、私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は『不思議な助言者、力ある神、永遠の父、